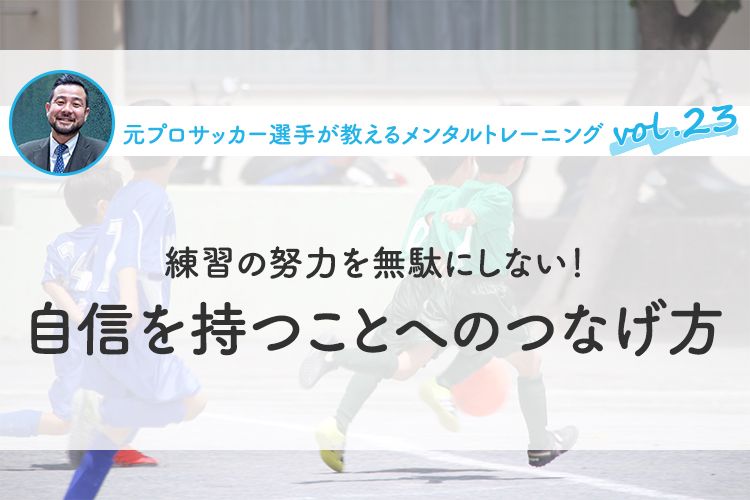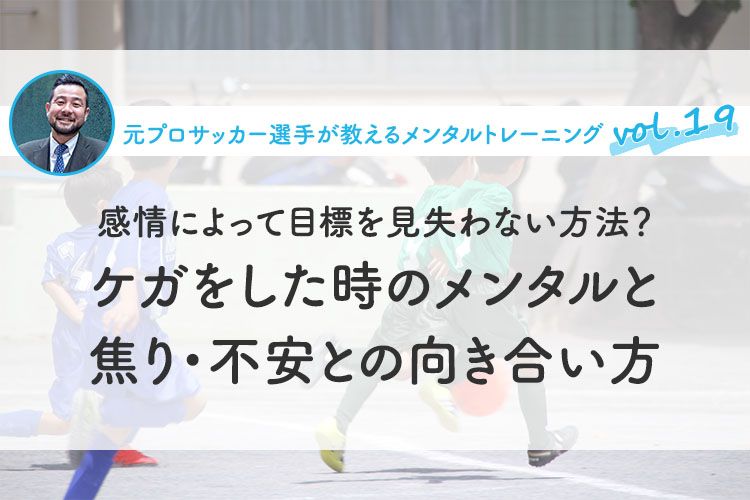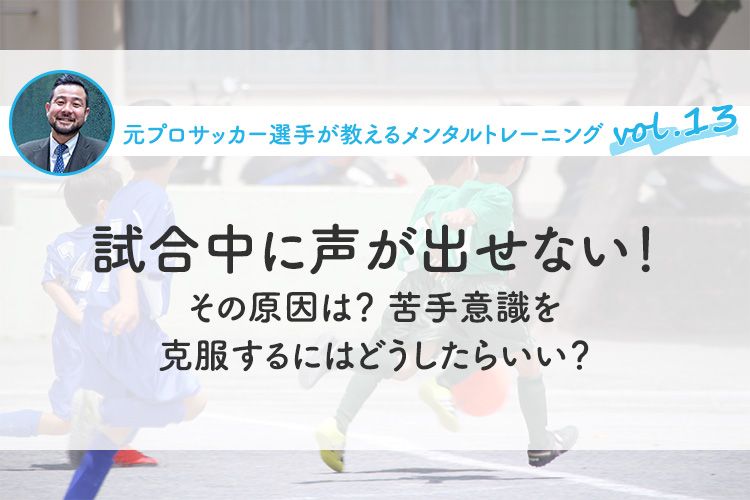子どもに自信をつける褒め方【サッカージュニアのメンタルを強くする!】
強い心を育むために大切な自己肯定感と自己効力感。これらを高めるには、褒め方が重要です!ここでは、子どもの自信を補う、褒め方のポイントをご紹介。
★メンタルが強い子に育てるには? 自己肯定感と自己効力感についてはこちら
本人が達成できた結果を褒める
そもそも自己効力感は、何かを達成できたという経験が必要です。達成できれば、その事実そのもので高まるので、親御さんは「よくやった」と嬉しそうな表情を見せるだけでもいいでしょう。なお、子どもができて当たり前だと感じていることを褒めると「この程度で褒められるくらい、期待されていない」と思うかもしれません。また、達成できた時だけ褒め続けると「できなくなったら、ダメな奴」と考えるようになりかねないので、注意が必要です。
ただそこにあるものを褒める
自己肯定感は、赤ちゃんの頃、親を喜ばせようとしているわけでもないけれど、ただそこにいるだけで喜ばれるという経験の中で培われていきます。そのため、本人が努力したわけでもなく、ただ持っているに過ぎない部分を褒めることで、自己肯定感が高まっていきます。「声がしぶくなってきたね」「肩幅がついてきたね」などと言うのも悪くないでしょう。
褒められると思っていないことを褒める
何かを頑張った時や自信を持っていることを褒められても自己肯定感は増えません。自己肯定感を高めるためには、「そこを褒められるなんて、思いもよらなかった部分」を褒めることです。また、褒められると思っていないタイミングで褒めるとより有効です。
子どもがしたことに感謝する
子どもが何かを頑張ってやり遂げた時、何かをしてくれた時に「助かった、ありがとう」と感謝することです。すると、子どもは「何かをした時にありがとうと言ってもらえる」「自分は他人を喜ばすことができる」と思うので、自己効力感が高まります。この方法が、自己効力感を高めるのに最も有効でしょう。
努力を褒める
努力を褒める時は、結果が出る前に褒めるのがベスト。というのも、結果が出た後、例えば試合に負けた直後に「努力したよね」と褒めても、慰められただけだと思うかもしれないからです。
そこにないものを褒める
褒めるところを探しても、なかなか見当たらない場合は、無理矢理つくるのも方法です。「ちょっとした仕草に品があるね」「なんか光るものを感じる」などと、子どもが持っていない部分を、あたかもあるように褒めるといいでしょう。褒め続けると人は変化するので、子どももその気になっていくものです。
あなたと過ごす時間が楽しいと伝える
あなたと過ごす時間が嬉しい、楽しい、幸せ……という感情が子どもに伝わること、また伝えることこそが、子どもが自己肯定感を持つ鍵になります。親御さんは、子どもが問題行動を起こしてしまうと、どうしてもこのような感覚を子どもに持ちにくくなり、その気持ちが態度や言葉で伝わり、子どもの自己肯定感を減少させてしまいます。親御さんが子どもに対する姿勢を前向きに安定させ、子どもをかわいがることで、「なんとかなる」という自己肯定感は育っていくのです。

参考/宮田雄吾「やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル」(日本評論社)、宮田雄吾「ストレスに強い人になれる本」(日本評論社)