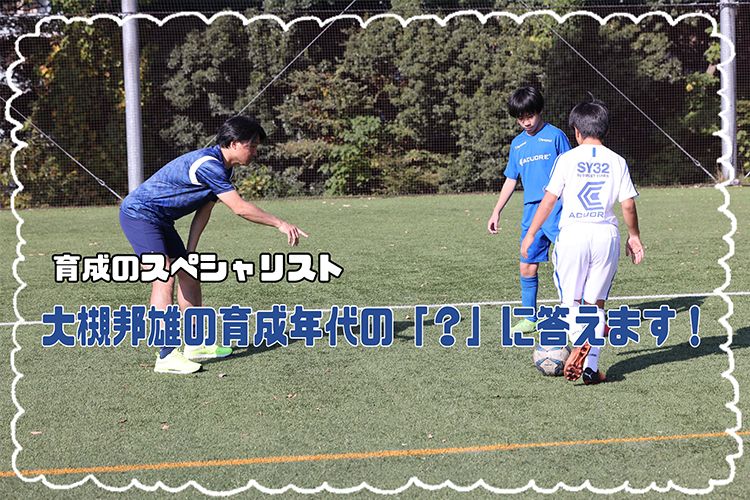「ベンチの悔しさ」を「成長の力」に変える保護者の心得【大槻邦雄の育成年代の「?」に答えます!】
サカママ読者の皆さま、こんにちは。大槻です。
気が付けば今年も残すところ僅かとなってきました。朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、グラウンドでは寒さも気にせずに走り回る子どもたちの姿に刺激を受けています。
さて、先日、ある試合でベンチから真剣にピッチを見つめる選手の姿がとても印象に残りました。試合後、彼は悔しさを滲ませながらも、一言「もっと練習します」と力強く言ったのが聞こえたのです。
いつも主役でいられるわけではありません。しかし、試合に出られず、「ベンチで悔しい思いをする」経験は、子どもたちにとって成長のための大きな壁であり、同時に大きなチャンスでもあります。
今回は、ジュニア年代を対象に「ベンチの悔しさ」を「成長の力」に変える保護者の心得について、具体的なアプローチを交えながら一緒に考えていきましょう。
保護者自身の「心の整理」と「家庭の役割」
「モヤモヤ」を認めて冷静になる
わが子が試合に出られないとき、親が「モヤモヤ」するのは、愛情と責任感の裏返しです。しかし、その感情に振り回されてはいけません。
《感情を客観視してみましょう》
「私は今、子どもが試合に出られず不安なんだな」と冷静に認めましょう。感情を抑え込むのではなく、整理することが、子どもと向き合う第一歩です。
《責任の所在》
「試合に出る・出ない」は、親御さんが決定することではありませんし、子ども自身は頑張って練習する以外は、コントロールできない部分が多くあります。子どもを責めたり、「下手だから」と否定したり、他人と比較したりすることは、自己肯定感を著しく低下させる行為です。
家庭は「安全基地」であってほしい
子どもにとって、家は学校やさまざまなストレスから解放され、エネルギーを充電する場所であるべきです。試合後の自宅や移動中の車内で〝反省会〟があるなんていうことも聞いたことがありますが...それは安心できる環境とは言えないかもしれません。
《聞き役に徹する》
人は気持ちを聞いてもらうだけでスッキリします。親はまず、子どもの悔しさや考えを遮らずに聞きましょう。アドバイスはその後です。
《平常心を保ちましょう》
親が深刻な顔をしたり、過度に気を遣ったりすると、子どもはさらにプレッシャーを感じてしまいます。いつも通り接し、好きなこと(食事、遊びなど)で頭を休ませる時間を提供してください。無理にサッカーの話を持ち出す必要はありません。

モチベーションを「外側」から「内側」へ
試合に出られない状況で、子どもの「やる気」(モチベーション)をどう維持させるか。大切なのは、「好きでいさせる努力」を大人がすることです。
「好き」の気持ちを絶やさない関わり方
本当に上手くなる子どもは、「もっとやりたい」「こうなりたい」という内側から燃え出てくる強い想いを持っています。その根本は、「サッカーが好きだ」という気持ちです。
《「楽しさ」の再確認》
試合後や練習後に、結果ではなく「今日の試合、楽しかった?」と問いかけてみてください。子どもが「次はこうしよう!」と前向きな言葉を発していれば、それだけで成長している証拠だと思います。
《過程と成長の承認》
技術的な結果だけでなく、目に見えない努力や成長の過程を承認し続けましょう。「今日の練習は集中していたね!」「あのプレーは失敗しちゃったけど、考えていることは良かったと思うよ!」など、小さな頑張りに光を当ててください。
《比較の禁止》
これは絶対に控えましょう。他の子との比較は、モチベーションを下げ、チャレンジを恐れる原因になります。心と体はアンバランスに成長します。個々の「今」を見極めて、その子自身の成長だけに目を向けましょう。
思考を「自分本位」から「状況本位」へ
試合に出られない選手は、焦りから「自分のいいところを見せたい」と、チームの状況を無視したプレーを選択しがちです。自分本位ではなく、チームの状況を優先したプレーを選択できると良いでしょう。
《課題の明確化》
悔しさを、単なる感情で終わらせず、「どうすればチームの勝利に貢献できる選手になれるか」という具体的な課題に昇華させましょう。
《ベンチを「学びの場」に》
ベンチにいる時間も試合の一部です。監督がどういう選手を求めているか、試合の流れをどう変えたいかを冷静に観察するよう促してください。試合に出られない理由を客観的に考える機会を与えることが、内面的な成長を促します。

効果的な指導者とのコミュニケーション
指導者と保護者の良好な関係性は、子どもにも大きな影響を与えます。指導者もお子さんの成長を願っています。指導者に敵対心を抱くのではなく、子どもたちのために建設的な関係を築きましょう。
親の「立ち位置」を理解する
私は指導者として活動する傍ら、一人の親として子どもの習い事の引率も経験しました。指導者とのコミュニケーションが難しいと感じる保護者が多いことも理解しています。
《指導者へのリスペクト》
指導者は、その子一人のためにチーム運営をしているわけではありません。チーム全体の成長と勝利という視点を持っています。まず、その指導方針と役割に敬意を払いましょう。
《役割分担の明確化》
指導者は「指導と育成、課題の整理」、保護者は「家庭での心身のサポートと生活管理」が主な役割です。互いの領域を尊重し合うことが、信頼関係の基盤となります。
建設的なコミュニケーションの原則とは?
感情的になったり、結果(試合に出る理由)だけを聞き出そうとしたりするコミュニケーションは、避けたほうが良いかもしれません。
《適切なタイミングを選ぶ》
試合直後や練習の準備・片付けの時間は、指導者が集中すべき時間です。話をするなら、事前にアポイントメントを取り、落ち着いた場所と時間で話しましょう。
《「問い」の視点を持ちましょう》
「なぜうちの子は出られないのですか?」と詰問するのではなく、「自宅で、どのようにサポートが必要ですか?」という、前向きな「問い」でコミュニケーションを始めてみてください。
これにより、指導者もあなたの協力を求められていると感じ、具体的に「足りない部分」や「家庭での取り組み」についてアドバイスしやすくなると思います。

まとめ
今回はジュニア年代を対象にして保護者の心得について整理していきました。どんな結果であっても、お子さんにとって一番のサポーターはお父さん、お母さんです。子どもがいつか振り返ったときに、「あのときがあったから、今があるんだ」と思えるような時間を過ごせるよう、信じて、冷静に応援し続けてください。
※心身ともに成長著しいジュニアユース年代の子どもたちへの保護者の関わり方については、あらためて別の機会に詳しく整理していきたいと思います。