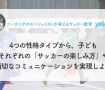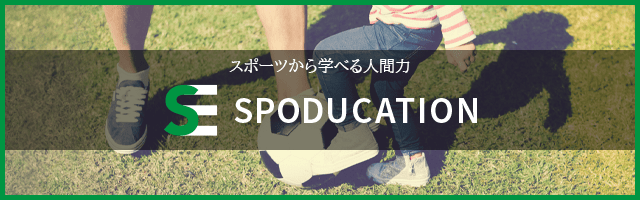Jリーガーたちの原点「上田 康太(ファジアーノ岡山)」
「負けず嫌い」の性格が手伝いサッカーに夢中になる
今シーズン、J2リーグで好調を維持しているファジアーノ岡山。中盤の底から試合の指揮を執るのが、昨シーズンジュビロ磐田から移籍してきた31歳のMF上田康太だ。的確な判断力と鋭い縦パスで、「岡山のサッカーの質を上げた」とまで言われる存在感を発揮。今季はその左足から、5月27日の町田ゼルビア戦を含め、鮮やかなフリーキックをすでに3発決めている。
「(チームの好調は)シーズン前のキャンプから、チームとして厳しいことをやっている成果だと思います。攻守ともに自分がチームの起点となるポジションなので、責任感を持って試合に臨んでいます。岡山は最後まで諦めないことを大事にしてきたチームですし、昇格するには最後はそこが大事になってくると思っています」
大宮アルディージャを経て、昨シーズンまではジュビロ磐田に在籍、そして今季、先述した活躍をみせる上田は、兄、姉の三兄弟の末っ子として東京・青梅で生まれ育った。サッカーをはじめたきっかけは父親の影響だったという。
「自分からやりたいと言った覚えはなくて、父から『サッカーをやってみないか?』と言ってもらったのが最初でした」
通ったのは小学校とは別の学校の少年団。当初は行くのが嫌で泣いていたこともあったという。しかし元来「負けず嫌い」だったこともあり、3歳年上の兄の友人達に交ざってサッカーに興じることで、メキメキとスキルを伸ばしていくことになる。
嫌で始めたサッカーだったが、上手くなれば当然楽しくなる。楽しくなればより、上手くなりたいとボールに触れる時間が増す。
「最初はできないことだらけ。リフティングの回数を増やすことから始めて、パス、ドリブルと、できることを一つひとつクリアしていっても、やることは無限にある。外はもちろん、家に帰ってもボールをずっと蹴っていて、もう時間も忘れるくらい夢中でした」
理想的な循環が、上田少年のサッカー上達に拍車をかけ、小学3年生の頃になると、周囲との実力差を自身でも肌で感じていたという。そして挑んだのが、ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ)の育成組織である読売サッカークラブのセレクション。“腕試し”だったというが、見事合格を手にした。
共働きだった母は時間を調整して毎日サポートしてくれた
青梅から稲城の練習場まで電車とバスで片道1時間半。小学3年生にとっては相当な距離と時間を要することになる。それまで楽しかったサッカーは、「競争」に様相を変え、過酷な日々が始まることとなった。
「上手い選手と練習できて、楽しかった反面、毎日が勝負というか、置いて行かれないように必死でした。少年団で高くなっていた鼻は、見事にへし折られましたね」と笑う上田だが、大きな環境の変化は小学3年生にとって、身体的にも、精神的にも負担になったことは容易に想像できる。そんな状況のもと、そばでサポートしてくれたのが、食事など生活面を支えてくれた母親だった。「学校から家に帰ってきたら駅まで送ってもらい、練習から帰ってくる遅い時間も、いつも駅で待っていてくれました。当然夕飯の用意も遅くなり、ほぼそれが毎日でしたから、母は本当に大変だったと思います。共働きだったのですが、母はどうにか時間を調整して、毎日サポートしてくれました。今となっては、当時の母がどれだけ苦労していたか分かるし、本当に感謝しています」
小学生後半の3年間、「とにかく上手いと感じてた」というヴェルディのコーチ陣から受けた影響は大きかった。シザース(ドリブル時に左右の足でボールをまたぐ技術)や、1対1の駆け引きなど、普段の練習から目の前に上手い見本があることで、感覚的にそれらを吸収することができたのだ。
「コーチと選手でゲームをして、負けると半面コートを、ビリになると全面をダッシュし、戻ってすぐにゲームに入る。僕は足が遅かったから、ビリの常連でエンドレスでした(苦笑)。正直、憂鬱にもなったし、辛かった。でも負けず嫌いなんですよね(笑)」
厳しい環境下でも、チームを包む空気は、陽気なラテンのそれに近かったという。コーチからは「こんなのもできないのか!」と叱咤を受けても、それでシュンとなる仲間はいない。「生意気なヤツばっかり」と表するチームメイトは、負けず嫌いな上田の肌に合っていたのだろう。ヴェルディで中心選手となっていた6年生時には、1試合で同じ選手に二度もまた抜きをされたこともあったが、それで心が折れることはなかった。むしろ「なにくそ!」という思いをやる気の燃料とし、上田の技術的な基礎は、この時期に徹底的に磨かれていった。

名波さんのプレーに心酔し、背中をずっと追っていた
中学時代は地元のレイソルS.S.青梅(現AZ’86 東京青梅)、高校年代はジュビロ磐田U‒18でプレー。U‒15~U‒17日本代表に名を連ねていた上田は、あらゆるチームからの誘いを受けていたが、進路はすべて自分で決めていたという。サッカーをはじめるきっかけを与え、積極的にアドバイスをしてくれた父親は、上田のヴェルディ合格後、そのスタンスを“見守る”立場へと変化させていた。
「僕のプレーを尊重してくれたのか、試合は見に来てくれましたが、少し距離を置いて、僕に考える余地をあたえてくれた。それがすごく心地良かったし、伸び伸びとサッカーに打ち込むことができました。だから進路も自分で考えて自分で決断し、両親はそれをまっ直ぐにサポートしてくれました」
静岡での寮生活となったジュビロ磐田U‒18時代。自身の能力に伸び悩みを感じ、高2の頃はこのままではプロになれないかもしれないとあせっていたという。しかし高3になり、ボランチなどを任されることで、自分のプレースタイルが確立していった。また、この当時、背番号7を背負い、トップチームの中心にいたのが、現ジュビロ磐田監督の名波浩氏だった。上田のプロ昇格後はチームメイトであり、昨年までは監督と選手の関係だった。
「名波さんのプレースタイルが大好きだったし、その背中をずっと追いかけていました。監督としての名波さんの要求には応えられなかったかもしれないけれど、これまで学ばせていただいた経験を、岡山のために全力で尽くしたいです」
覚悟を持ってJ1昇格を目指す上田から、最後にサカママへメッセージをいただいた。
「僕は『サッカーが楽しい』というきっかけを、両親からもらい、好きなことを見つけることができて、よかったと思っています。サッカーに限らず、親としていろいろなきっかけや可能性を子どもに与えてあげること、そして、自由にさせて見守ることが重要なのかなと思います」
2018年7月発行の26号掲載