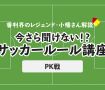実録! ジュニアのコーチはどう見ている? ~街クラブのとあるコーチの場合~
サカママ・サカパパのみなさん、こんにちは。ライターのYUKARIです。新年度がスタートし、2カ月ほどが経ちました。新しくサカママ(サカパパ)ライフが始まった親御さん、チームを転籍して新しい環境が始まったご家庭、学年が変わりこれまでとは違う指導者のもとでサッカーをすることになったお子さんをサポートする立場となった皆さん。そろそろ自チームに慣れ始めた頃でしょうか。
普段はジュニアユースのクラブチームに所属する息子の話題をメインに綴っている私ですが、今回は、息子がジュニア年代で所属していた街クラブでコーチを務める夫に話しを聞いてみました。夫は息子が小学校を卒業した後も、彼の古巣である街クラブでコーチを続けている現役指導者です。今はもう我が子がジュニア世代ではないからこそ、フラットな目線で「こんなとき、コーチはどんなふうに思っているのか」というダイレクトな気持ちを夫にインタビューしてみました。世の中にはチームの数以上に指導者もたくさんいますので「とある街クラブのとあるコーチの場合」といった背景を想像しながら読んでいただければ幸いです。

こういうタイプは成長が楽しみだ! と思う子はどんな子?
息子がいたジュニアのチームは、昔も今も変わらない典型的な「街クラブ」。所属する選手のほとんどが同じ小学校に通い、コーチの大半はもともと選手のパパさんだった、というきっかけから今に至るという環境です。勝つことばかりに拘るタイプのチームではなく、集まってくる選手は十人十色です。そんななか、コーチという立場から今後の成長がより楽しみに感じる選手とはいったいどんな選手なのか、夫に聞いてみました。
秀でた特徴が1つでもある
足が速い、ヘディングが強い、競り合いなら負けない、体格がしっかりしているなど「自分の強み」と自信を持って言えるような特徴がある。
ボールとの関わり、距離感を常に意識している
常にボールに関わろうとする姿勢があり、プレーに積極性がある。自分がボールを持っていないときの動きもちゃんと意識して動いている。
自分がやるべきことを言語化できる
練習や試合後の振り返りで「あのとき、あそこにパスをしたのはどうして?」「あそこでどうしてあのプレーをやろうと思ったの?」といった問いかけに、自分の言葉でちゃんと答えることができる選手。とくに男の子は本能でプレーをしている子が多いと思うので「言語化できる」という基準はとてもハードルが高いように思うかもしれませんが「仲間にパスしようとしたけど、近くに相手チームの子がいたからパスをやめて自分でドリブルをした」という回答も立派な「言語化」です。

トレセン選考について思うこと
普段、スマートフォンで少年サッカーやジュニアユースに関する検索をすることが多いからか、Xのフィードに自然と挙がってくるのが「トレセン」に関する保護者の心の呟きです。我が子の選出をかけて一喜一憂する投稿を見かけることも時にあります。
息子が現在所属するクラブチームは選手を地域トレセンに選出しないというスタンスのため、我が家では親子共々これといった緊張感はないのですが、コーチとしてチームから数名選出する立場にいる夫にとっては、また事情が違うようです。どの子も可愛く、どの子も頑張っている姿を知っているからこそ、その時期になるといつも頭を悩ませていました。そんな夫に「そもそもトレセンにはどういう人が選ばれると思う?」と聞くと、こんな回答が返ってきました。
①選考基準は各地域によって変わってくると思うが、大前提としてあるのは基本的な技術(ボールを止める、蹴る、運ぶ)とコミュニケーション能力
②チームワークを乱さない人柄
③自分の強みを出し切るメンタルの強さ(自ずとプレーに出てくる)
これらの回答を聞いて、私としては①の「コミュニケーション能力」という点にいまいちピンとこなかったのですが、その理由を聞いてみると、実際にトレセンの選考時に行われるゲームでは、その場で組まれたチームごとに、選手同士が話し合ってポジション決めをすることがあるそうです。そんなときに、仲間の意見に耳を傾けながらも、どれだけ自分をアピールしポジションを獲得するか、という点において「コミュ力」はとても大切な要素と言えるでしょう。

保護者に求めるサポート体制
ジュニア世代、とくに街クラブは保護者のサポート無しには運営も指導も成り立たない、というのが現状です。幸い、これまで指導をしてきた担当学年の保護者の方々にはとても恵まれている夫ですが、今回のコラムを書くにあたり「コーチとして保護者に求めることってどんなこと?」とあらためて聞いてみました。
・できるだけ我が子の試合を見に来てあげてほしい
・どんな結果でも否定しない
・保護者は指導者ではなくベストサポーター
・「何点とった?」「勝った?」という声掛けではなく「今日は楽しかった?」「新しいことにチャレンジできた?」など、子ども自身でその日を振り返ることができるような前向きな声掛けを
どれも「そんなの当たり前じゃない?」と思ってしまいそうですが、自分が当事者だったらどうかな…とふと我に返りました。我が子のことに熱くなるばかり、つい自分本位な言葉が出てしまいがちなものです。「自分(=親)がどうしたい」ではなく、あくまでも子どもを主語に考えて発言し、行動する。その立ち位置をいつも忘れずにいたいですね。

コラムのネタに…と夫へのインタビューを思いついた私ですが、その過程で息子のジュニア時代を思い出しました。当時の私はどんなサカママだったのだろう。息子にとって伸び伸びとサッカーに打ち込める雰囲気を作ってあげられていただろうか。今となっては、そうせざるを得ない場面も多々あったかもしれませんが、今でも息子が「サッカーが好き」という気持ちを失わずに切磋琢磨している姿に元気をもらいつつ、引き続き「ベストサポーター」としての立ち位置を忘れずにいたい、と気持ちも引き締まりました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。私の経験談が、誰かのお役に立てることを願って…。
選考課題としてよく話題に挙がってくる「リフティング」ですが、その場で止まったままリフティングをする、というよりも、決められたコースや距離をリフティングしながら移動する(歩く)というチェックもよくあるようです。トレセンを意識している人もそうでない人も、ときどきそんな練習をしてみると、普段のプレーに何かプラスに働くかもしれませんね。