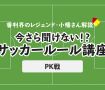この選択は正しかったのか? ジュニアユースでの3年間を振り返る
先月、息子が所属のジュニアユースチームの引退を迎えました。夏に続いて高円宮杯でも全国出場を目標としていましたが、あと一歩のところで力及ばず。それまでも対戦相手に勝利する度に、試合後のスタンドへの挨拶で涙を流している相手チームの選手の姿を目にし、「いつか息子にもそんな時が…」と思うともらい泣きしていた私でしたが、いざ我が子がその立場となると、「あれ、もう終わったの?」と、号泣というよりは茫然とする自分がいました。
3年間担当したコラムの執筆も今回で最後となります。思えば、息子がジュニアユースのセレクションを受ける際に、「もっといろいろな情報があったらなぁ」と思っていたことをきっかけに、これからセレクションを検討しているサカママ・サカパパに向けて自分の経験談で何か少しでも役立つ情報を発信できたら、という思いでライター応募をしたことが始まりでした。
本人にとっては「チャレンジチーム」でもあった、いわゆる「強豪」と言われるクラブチームでの3年間。私にとってそれは、奮闘する息子の姿を応援しながら執筆した3年間でもあります。
引退を迎えた今、あらためてこの3年間を振り返りたいと思います。

チームメイトは強豪チーム出身ばかり! 今までにない競争社会の毎日だったU-13
過去のコラムでも何度か書いていますが、息子が入団を決意したチームは、全国大会出場経験が何度もある彼にとって「チャレンジ」とも言えるチーム。チームメイトも、それなりのレベルのある子が揃っていました。ジュニア時代は毎回のように試合に出場し、ゴールを決めていた息子でしたが、新しい環境では毎週発表されるベンチ入りメンバーの発表に一喜一憂する毎日でした。
慣れない中学生活に加え、グラウンドの往復移動、平均3時間の練習が週4回。フィジカル的にも辛い練習や時に厳しい指導など、それまで彼が身を置いてきた環境とは180度違う世界だったと思います。それでも頑張り続けられたのは、仲間の存在や、尊敬できる監督・コーチ陣の存在。さらに、あることをきっかけに夏休みにふと覚醒したことで、息子にとっても「自信」が芽生えた経験があったからでしょう。
スランプ、そしてケガ、手術、リハビリで過ごしたU-14
調子が良いプレーが長く続くとは限りません。身体的にも肉体的にも無限の可能性を秘めたこの時期、ふとしたきっかけで一気に成長を見せる選手はたくさんいます。と同時に、その後のプレーがなかなか振るわない選手がいるのも確かです。
U-13の夏に大きな成長を見せた息子でしたが、その後はなかなか思うようなプレーができず…。今思えば、その悔しさと共に張り詰めた緊張の糸が切れかかっていたのでしょうか。あるチームメイトからの、息子のプレーを揶揄する発言をきっかけに、初めて息子から「チームを辞めたい」という言葉が発せられました。
なんとなくいつもと違う様子を感じていたものの、そこまで思い詰めていたとは…。でもこのときまだ救いだったのは、「サッカーを辞めたい」ではなく「チームを移籍したい」ということ。サッカーを嫌いにならなかったのは親としても本当に救われました。監督にも事情を説明し、ありがたいことに引き留める説得までしていただき、息子にとってもそれが心の支えにつながり、「もう一度このチームで頑張りたい」と決意できるようになりました。
さぁ、新たなステージに向けて頑張ろう! という時に訪れた「ケガ」・「治療」・「手術」・「リハビリ」という長い期間。U-14の夏以降、息子はボールを蹴ることすらできない状態となりました。
サッカーも勉強も集大成を迎えたU-15
約11カ月という月日を経て、息子が本格復帰を迎えたのは3年生(U-15)の夏休み前でした。それまで自主練などほぼしなかった息子が、自発的に筋トレやランニングに勤しみ、練習に参加できない状況でもグラウンドに足を運び、遠征試合でも応援にかけつけていた姿は、今思い返しても本当によく頑張ったなぁ、と我が子ながら感心します。
でも、この期間があったからこそ、息子の「サッカーが好き」という想いが確固たるものとなり、最終的な目標としていた「高円宮杯のメンバー入り」という結果への原動力になったのだと思います。
そして、U-15世代にとってサッカーと同じくらい大切なのが卒業(卒団)後の進路。息子のチームはユースのカテゴリーがないため、高校でサッカーを続けたいのであれば、自分でその道を切り開いていくしかありません。ただ、そうした背景からか、進路に関するサポート体制はとても手厚いと個人的には感じています。
例えばチームの監督と親交がある高校の場合は、チーム単位でその学校への進学を希望する選手を集めて練習会(という名のセレクション)に参加する機会が設けられ、最終的には自分のプレーを認めてもらい、且つその学校が求める基準の成績を収めていると判断されると推薦をもらうことができます。実際に息子のチームからスポーツ(=サッカー)推薦で進路を決めた選手は全体の約9割。「全国大会出場」というチームの功績がプラスに働いた子もいたようです。
学力で推薦枠を取る生徒がいる一方で、3年間のすべてをサッカーに捧げ、ほぼ休みなしで練習と試合に青春時間を費やした結果、サッカー推薦枠を手にする選手もいる。親としてはつい「勉強が」「成績が」と口を出してしまいそうになりますが、こうした結果も彼らが努力して自ら手にした進路選択ですね。

振り返ってみてどうだった? 親子で思うこと
既に引退を迎えている息子のチームのU-15世代ですが、卒業後もサッカーを続ける子がほとんどなので、チームの活動がある日はグラウンドの一部を提供してもらい、体力や技術維持のため、自由にプレーをすることが許可されています。時には後輩チームと対戦することもあるようです。なので、実際には「引退」というイメージが湧かないのが正直なところですが、実質的な引退を迎えた今、息子に「このチームに入ってどうだった?」と聞くと「あの時辞めないで本当によかった。このチームでプレーできてよかった」と自信をもって答えてくれました。私も本当に息子と同じ気持ちです。
きっと親には言えない、言えていないたくさんのプレッシャーや悔しい思い、逃げ出したくなる気持ちもあったかと思います。でも、それを乗り越え、ケガによる離脱という辛い時期も克服し、諦めない気持ちでここまでこられたのは、他ならぬ息子自身の強いメンタルとポジティブ思考があったから。必ずしも試合に出ることがすべてじゃない、そう思えたから。そして、「サッカーが好き」という揺るぎない心の支えがあったから。
お疲れ様。そして、たくさんの景色を見せてくれてありがとう。サカママの私から息子に一番伝えたい思いです。
最後になりましたが、これまでコラムを読んでくださった読者の皆様に心よりお礼申し上げます。私の経験談が少しでも誰かのお役に立っていたのなら幸いです。
私のサカママライフはいよいよ「高校サッカー」というステージへ…。