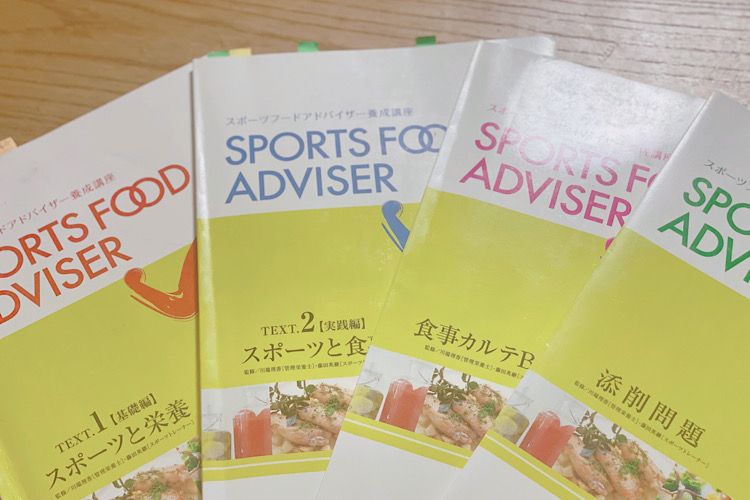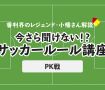ケガを予防するために子どものカラダを見てみよう
今回はケガを予防するためのご両親へのアドバイスです。
ある研究で現在の小学校3、4年生は、25年前の5歳児の運動発達段階ともいわれます。ロコモティブシンドローム(子どもに広がる運動機能障害)の言葉を聞いたことのあるご両親も多いのではないでしょうか。本来は年配の方に多い疾患でうまく歩けない、長時間立つことができない、重たいものを持つことができない、腰や膝が痛いといった同じような機能障害が現在の子ども達に蔓延しているのです。このような現状が社会問題になっていて文科省も4年前から体力テストに加えて、運動器事前検診をおこなうようになりました。
「ロコモティブシンドローム」は運動経験の少ない、あるいは運動不足の子どもに限った話ではなく専門的にサッカーに取り組んでいる「サッカー少年」にも見られる現象になっています。NHKの番組でも取り上げられていましたが1週間に10時間以上サッカーに打ち込んでいる子どもの偏った発達として、ふくらはぎや太ももなどの筋肉(量)が過度についてしまい、柔軟性や運動機能のバランスが損なわれ、しゃがめない、しゃがんだ状態から立つことができない、股関節を曲げて前屈ができないなどの運動機能障害が増えている内容でした。
原因は偏り...
低年齢からひとつの種目に特化し、偏ったスキルや運動をしているからにほかならない。勝つためを強く求めるがゆえに戦術中心の偏ったトレーニング(指導)をすることで体力(運動能力)の偏り(低下)に拍車をかけている事実を知りましょう。
予防するには...

サッカースクールばかりでの運動に終始せずに、オフの期間などを活用してサッカー以外の「遊び」要素でカラダを動かすことが重要です。楽しいと思えると脳はリフレッシュして心身の緊張も緩和させてくれます。定期的なオフはぜひご家族でレジャーに出かけてください。特別な運動は必要ありません、サッカー以外の要素で遊んで笑って、一緒に食べて過ごすことでケガの予防になるのです。
サッカーコーチは勝つための戦術と専門的体力トレーニングを担当し、ご家族は遊ばせる担当を担ってあげてください。ライフバランスを整えるご家族は、いわばコーディネーターです。専門的な生活ばかりでは子どもは疲れてしまいます。明日への活力アップが成長の可能性を高め身体の成長を促進させることをもう一度考えてみてほしいと思います。