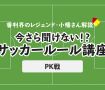撮る場所で変わるサッカー写真の物語性。撮影場所を戦略化しよう!
サカママ読者のみなさま、こんにちは。9歳と6歳の二人の子どもを持つ、サッカーとカメラをこよなく愛すReikoです。約2年間に渡り、サカママライターとして書かせていただいたこちらのコラムも今回を以って最終回となります。カメラネタをはじめ、さまざまなテーマで「子どもとサッカーをつなぐ」お役立ち情報を配信させてもらい、学びの多いとても楽しい2年間となりました。これもひとえに、コラムを読んでいただいている読者のみなさまのおかげです。本当にありがとうございます。
最終回のコラムを書くにあたり、どのようなテーマにするかすごく悩みましたが、サカママライターとしてご縁をいただいたきっかけが「カメラ」というのもあり、最後のコラムはカメラにまつわるテーマで締めさせていただきます。

サッカーの試合撮影というと、「どんな機材を使うのか」「カメラの設定はどうするのか」に目が行きがちですが、同じくらい(むしろそれ以上に)違いを生むのが撮る場所の選び方です。撮影をするポジションはただの立ち位置ではなく、写真に込められる「物語の視点」そのものです。
タッチライン中央で撮れば選手入場や試合開始前の円陣、試合中の様子をまんべんなく撮ることができます。その日の試合がどう動くのか、どのサイドを崩そうとしているのか。「流れを読む力」が身につくのは、サイドライン撮影ならではの魅力かもしれません。
一方で緊張と期待が交差し、「静と動を最もドラマチックに切り取り、物語が生まれる場所」でもあるゴール裏。ゴールライン側から撮れば、ゴール前の攻防、シュートシーン、得点の瞬間の歓喜が表情と共に写ります。「撮影設定を変えているのに、なんだか写真が代わり映えしない…」そんなときは、実は撮影ポジションが固定されすぎているのかもしれません。
撮る立ち位置を変えるだけで、同じレンズを使っていたとしても、写真の見え方は変わります。では実際にどういうところに意識をするのか、詳しくご紹介していきます。

低めの目線vs高めの目線。写真の印象を大きく変える「高さ」の力
撮影位置というと横移動に目を向けがちですが、「高さ」の選択もとても重要です。写真撮影全般に言えることですが、地面すれすれの低い目線は、選手を大きく、力強く見せ、選手たちの躍動感を引き出してくれます。頑張る姿をドラマチックに残したいなら、低い位置での撮影は外せません。
逆に、観客席の少し高い位置から撮ると、全体の流れやチームプレーの関係性が見えてきます。あの日、スタンドの上段から撮った写真には、ゴール前へ走り込む我が子と、パスをつなげてくれた仲間、後ろからチームを支える守護神…一つのプレーを取り巻く「仲間の物語」が写ります。

近づける場所に自分が動く。シーンごとのおすすめポジション
応援場所の指定がない場合、カメラで試合を撮影する際には必ず試合前のポジション確認から始めています。仮に我が子は今日右サイドだと分かった時点で、子どもの近くに寄っていきます。攻めている時のドリブル、縦突破の瞬間、シュートシーンを極力正面に近い角度から狙うためです。高額な超望遠レンズでない限り、ズームレンズにも限界があるため、できるだけ「近づける場所に自分が動く」のが戦略の肝です。
慣れてくると子どもの動きに合わせて自分自身も動けるようになり、そうすることによって被写体に近づけ、ピントが合わせやすくなります。多く撮影すればするほど、どのポジションで撮れば良いのかがだんだん分かり、
・ドリブルのスピード感
・キックの予備動作
・ゴールへの軌道
・チームメイトとの距離感
など、臨場感のある写真として残せるようになり、これを意識するだけで撮れる世界は大きく変わります。
また、
・コーナーキック→コーナー付近
・ビルドアップ→タッチライン中央
・ゴール前の攻防→ゴールライン寄り
というように、シーンや撮りたいイメージによって少しずつ場所を変えることで、「試合の物語」を写真の中に散りばめることができます。
注:必ず大会規約で定められているルールを守りながら撮影を行いましょう
意識だけで変わる。写真の仕上がりを変える小さな工夫
撮影する位置を戦略的に選ぶようになると、自然とどこに立つのが一番良いのか感覚で分かるようになります。また、ほんの小さな意識の工夫が写真の仕上がりを大きく左右します。
一つが背景の写り込みを少しだけ意識すること。
ジュニアサッカーだとピッチがまだ小さく、一つのグラウンドに複数のコートがあることも多いなかで、被写体の後ろのごちゃつきの原因となっている隣のコートの観客、ベンチ、駐車場の車などを避け、同じ位置からの撮影でも2歩右にずれてみたり、カメラを構える高さを変えてみたりと、混雑を避けた角度に意識を向けます。
二つめが動く方向に余白を作ること。
これも技術ではなく、意識だけで変わります。ボールを追いかけている方向やパスを出す方向側に余白を作り、次の動きの予測を想像させることによって、物語性のある写真が生まれます。
三つめが撮らない勇気を持つこと。
精神論のようで、合理的な方法なのですが、すべてのプレーを追わず、ボールが遠いとき、背中を向けていて良い画にならないとき、人が密集していて被写体を見つけ出すのが難しいときなど、あえてカメラを下ろしてみましょう。カメラを構えないことで、次の「撮れる瞬間」へ集中ができ、ヒット率がぐんとあがります。

コラムを書かせていただいたこの2年間、カメラのこと、子どもの成長のこと、ワーママとしての葛藤のことを読者のみなさまと一緒に考え、悩み、楽しみながら書き続けてきました。サッカー写真はただの記録ではなく、写真を見返したときに、そこには「あの日の気持ち」がよみがえります。ドリブルで相手を抜いた瞬間の誇らしい表情、悔しくて涙をこらえた後ろ姿、仲間と肩を組んだあの一枚。すべてが親子の宝物になっていくのだと思います。カメラは奥が深く、難しい点もある一方で、少しの意識の変化で写真の見え方が変わり、新たな物語として思い出を残すこともできます。
これからも子どもたちの成長の瞬間が、みなさまのカメラにやさしく、力強く刻まれていきますように。サカママとして、写真を愛するひとりの母として、この2年間応援してくださったみなさまに心から感謝いたします。
本当にありがとうございました! またいつかお会いしましょう!