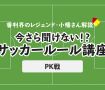アメリカのジュニアサッカーは「4→7→9→11人制」で選手を育てる! “子どもの発達段階に寄り添う”育成システムの意義
こんにちは、テキサスのサカパパjapa-ricanです! 私がアメリカジュニアサッカーの世界に足を踏み入れて最初に驚いたことが、11人制サッカーが始まるまでに、年齢に応じてプレーする人数が細かく変化していくことでした。今のアメリカでは、キーパーなしの4人制サッカーから始まり、7人制、9人制、そして11人制へと段階的に移行するシステムが採用されています。
幼少期から試合の楽しさを感じ、成長に合わせて自然にチームプレーを学べるこの仕組み。試合経験を通して選手を育てようとするアメリカジュニアサッカーの哲学が見受けられます。今回は、その背景や目的、そして日本やヨーロッパとの違いについてご紹介します。
私の時代は小学4年生から11人制だった
私がサッカーを始めた頃(1990年代)、日本では小学4年生から11人制サッカーをしていました。当時は背の低いゴールキーパーが届かない高さのシュートに泣かされることも多く、広いグラウンドを走り回るのは体力的にも大変でした。
その後、日本サッカー協会は2011年から、U-12世代までに8人制を導入。選手数を減らすことでボールタッチ数を増やし、判断力やテクニックの向上を狙いました。しかし、ここアメリカではさらに細かい段階を設けたシステムが取り入れられています。
4人制から始まる「スモールサイドゲーム」制度
アメリカでは、U.S.サッカー連盟(U.S. Soccer Federation)が2016年に全国統一ルールとして導入した「スモールサイドゲーム(Small-Sided Games)」という制度があります。これは、子どもたちの年齢や体格に合わせて試合形式を変えるもので、年齢が上がるごとに少しずつチーム人数を増やしていくのが特徴です。
年代ごとの試合形式の変化
| 年代 | チーム人数 | フィールドサイズ | 試合時間(目安) |
|---|---|---|---|
| U-5〜U-6 | 4人制(キーパーなし) | 約20×30m | 前後10分×2 |
| U-7〜U-8 | 4〜5人制(キーパーあり) | 約25×35m | 前後20分×2 |
| U-9〜U-10 | 7人制(7v7) | 約40×55m | 前後25分×2 |
| U-11〜U-12 | 9人制(9v9) | 約50×70m | 前後30分×2 |
| U-13以上 | 11人制(11v11) | 通常サイズ | 前後35〜45分×2 |

目的は「より多く、より楽しく」学ぶため
この制度の一番の目的は、子どもたちが年齢に合った環境で、より多くのプレー体験を積むことです。例えば4人制(上記の写真)では、全員が常にプレーに関わり、ボールに触る回数も多くなります。一試合でのボールタッチ数は11人制の約5倍とも言われ、自然とボールコントロールや判断力が磨かれます。次にゴールキーパーを含め7人制(下の写真)へと移行し、オフサイドも適用されるようになります。

また、小さいフィールドでは一瞬の判断が勝敗を左右します。味方との距離感やスペースの使い方を覚えることで、「見る力」「判断する力」を早い段階から養うことができます。
多くの試合で得られる経験値
アメリカでは「練習よりも試合で学ぶ」という考え方が強く、週末はリーグ戦がびっしり詰まっています。
私たちの住むダラス近郊では、U-5(4歳)からすでにリーグ戦が行われており、小さな頃から実戦を豊富に重ねられるのがアメリカらしい大きな特徴です。
リーグ戦が中断する冬場や、シーズンの集大成となる5月・6月には、大小さまざまなカップ戦が毎週末開催されます。一つのカップ戦で3~6試合ほどの真剣勝負を経験できるため、リーグ戦と併用すれば、クラブによっては小学1年生から年間30〜40試合を行うことも珍しくありません。今シーズンはU-10とU-11でプレーする息子は、おそらく年間で50~60試合をこなす見込みです。
試合を通じて、成功体験や失敗を大量に積むことが、子どもの成長を強く後押ししていくというのが、アメリカジュニアサッカーの基本的な考え方のようです。

課題もある
もちろん、試合数が多い分、課題もあります。
•練習よりも試合に重きを置きすぎて、個人技術の積み上げが不足しがち
•一部のチームや保護者が、勝敗を重視しすぎてしまう傾向
•地域や指導者によって、制度の理解や指導レベルに差がある
制度そのものは優れていますが、「どう活かすか」は結局のところ現場の指導者次第です。
また、複数のリーグ戦やカップ戦への参加は強制ではないため、経済的な負担も考慮し、親が子どもと相談して決めることが一般的です。そのため、保護者たちも子どもの精神的・肉体的な状態を注意深く見守ることが必要です。
私自身、どこまで息子に試合をさせてあげるかについては、息子の「サッカーが大好き」という純粋な気持ちを守ることを最も大切にしています。

世界各国との比較
この「年齢に応じて段階的にチーム人数を増やす」という考え方は、アメリカだけではなく、ヨーロッパのサッカー先進国でも取り入れられているようです。
チャットGPTで調べてみると、イングランドやスペインなどでは、年代ごとにプレー人数を変える仕組みが導入されているようです。
•イングランドFA(イングランドサッカー協会)
U-7〜U-8:5人制/U-9〜U-10:7人制/U-11〜U-12:9人制/U-13以上:11人制
•スペイン
U-8までは5人制、U-10〜U-12は7人制。地域によっては9人制を採用しているところもあるようです。
アメリカもこうしたヨーロッパの取り組みを参考にしながら、広大な国土を活かして全国的な統一ルールを整備したとも言われています。
とはいえ、各国の制度は地域差や連盟ごとの方針によって異なることもあります。世界各国ではジュニアサッカーでの人数をどのように設定し、どんな段階を経て変化させているのかを比べてみるのもおもしろいかもしれませんね。
「試合で学ぶ」文化と個人育成哲学の違い
アメリカでは「練習よりも試合で学ぶ」という考え方が徹底されており、地域によって差はあるものの、私たちの住むダラス地域では4歳から試合に出られる環境が整っています。
子どもがゴールを決めて喜び、負けて悔しくて泣く——こうした感情を揺さぶられる実体験を通して、サッカーは純粋な「遊び」から「自分のもの」へと変わっていきます。
日本の育成現場では、個人としての技術向上が最も重要視される傾向が見受けられるため、リフティングの回数やコーンを使ったドリブル練習などに多くの時間が取られているように感じますが、ここアメリカでは、「チームとして試合に勝つことに全力を向ける」という、サッカーの本質的な部分が育成の軸にあるように感じています。
どちらもサッカーにおける正しい価値観であり、単純な優劣比較はできません。しかし、親としても指導者としても、日米それぞれにこのような異なる育成文化があることを理解しておくことが大切だと痛感しています。
先日チリで開催されたFIFA U-20ワールドカップでは、日本代表は惜しくもベスト16で大会を去りました。一方、アメリカ代表はベスト8まで進出し、敗れはしたものの、その準々決勝では優勝したモロッコを相手に健闘を見せる結果となりました。
ジュニア年代で圧倒的なボール技術を習得する日本サッカーが、世界の強豪国との一発勝負のトーナメントで苦戦が続く裏で、幼少期から「勝ち負け」に徹底的にこだわる中で育ったアメリカの選手たちが国際舞台で結果を出す。この対照的な現実に、私はいつも日本の育成のあり方を深く考えさせられるのです。
そして、2026年のW杯で日米それぞれの代表がどんな結果を残してくれるのか大変気になるとこです。私と息子は大の日本代表ファンなので、ここアメリカから全力でサムライブルーを応援しています!

発達段階に寄り添うシステム
アメリカのジュニアサッカーは、4人制から始まり、子どもの成長に合わせて自然に11人制へと移行していくシステムを採用しています。
このシステムの背景には、“発達段階に寄り添った環境づくり”という明確な哲学があります。国や文化が違っても、ボールを追いかける子どもたちの笑顔は同じです。この仕組みの根底には、「まずは子どもたちにサッカーを心から好きになってもらう」という、普遍的で大切な願いが込められているように感じています。