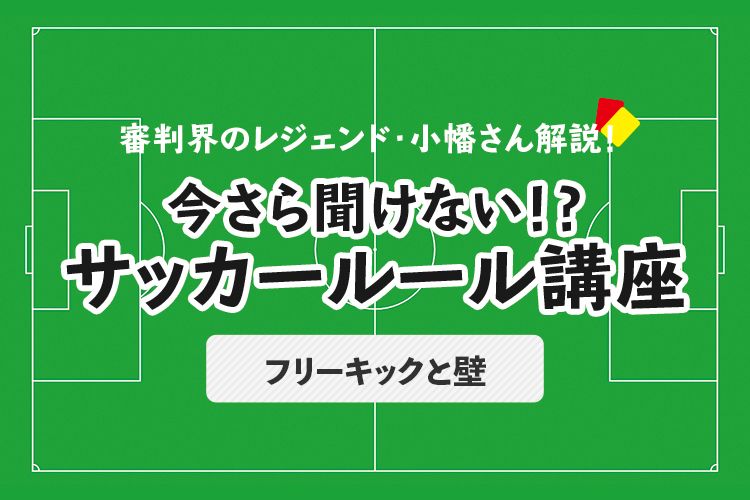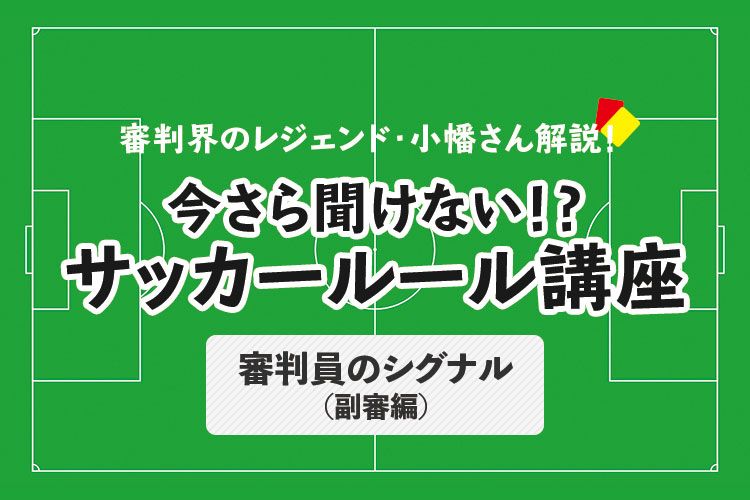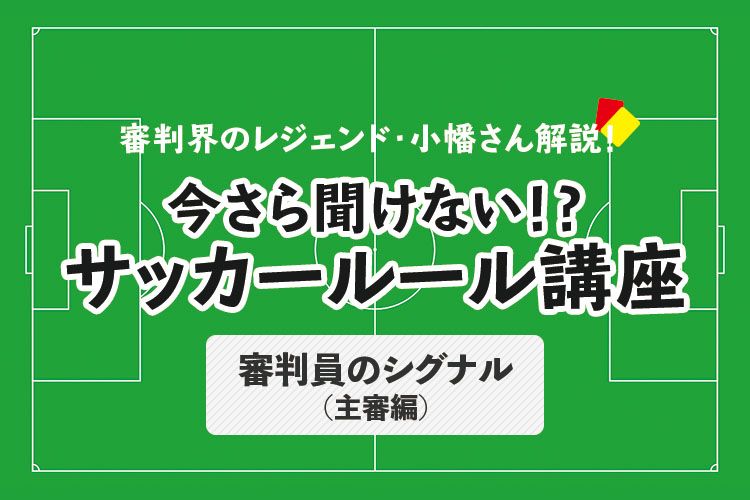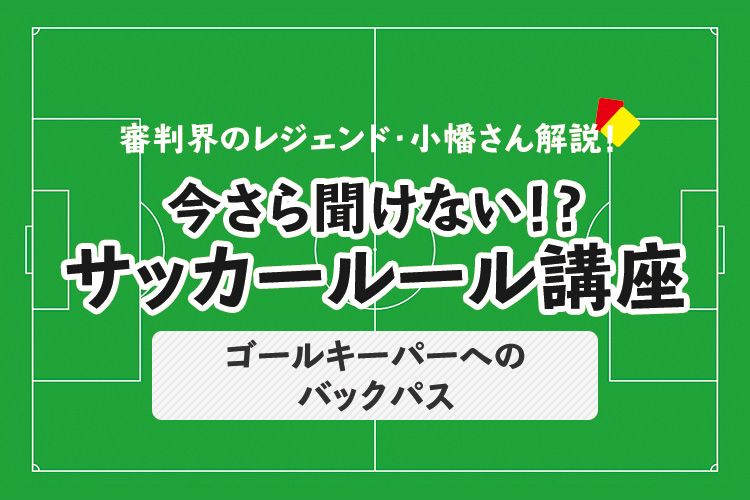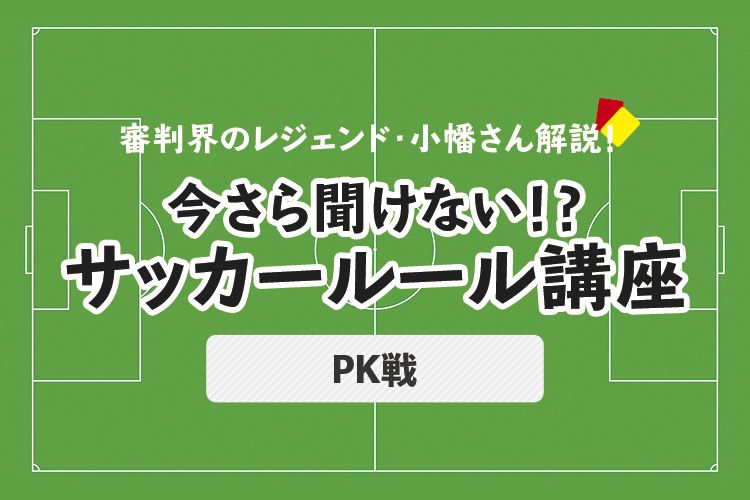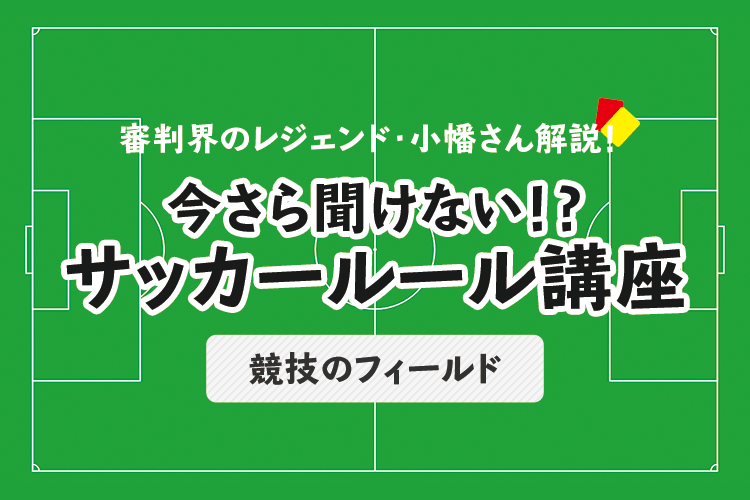今さら聞けない!? サッカールール「2025/26年 競技規則の改正」
1993年のJリーグ開幕戦で主審を務め、審判界に多大な功績を残したレジェンド・小幡真一郎さんによるサッカールール解説シリーズ! 今回は、2025年7月から新たに導入された競技規則について解説します。
規則改正は何のために行われるの?
競技規則改正の季節がやってきました。
サッカーの競技規則はサッカーの魅力を向上させるため、またサッカーの置かれている環境変化に対応するため、毎年、国際サッカー評議会(IFAB)によって制定、改正・変更され、フェアなサッカーが展開されるようになっています。
この競技規則が有効になるのが7月1日ですが、競技会(リーグ、大会、地域・都道府県協会など)によって有効となる日程は異なります。国内では、最も早いのは各種全国大会で、7月25日(金)から2025/26 を適用しています。Jリーグ1部は8月9日(土)第25節から適用しています。
今回は改正・変更されたものから、次の4点を取り上げます。
①ゴールキーパーが8秒を超えてボールを保持した場合、相手側チームにコーナーキックが与えられる(第12条 ファウルと不正行為)
②ドロップボールによる再開方法が変更になる(第8条 プレーの開始および再開、第17条 コーナーキック)
③キャプテンオンリー:主審は基本的にキャプテンに対して重要な判定を説明することができるようになる(第3条 競技者)
④チーム役員などが競技のフィールドから出ようとするボールに触れたが、不正に妨害しようとする意図がなかったときの再開と懲戒の罰則の考え方が追加される(第9条 ボールのインプレーおよびアウトオブプレー)
順に詳しく見ていきましょう。

ゴールキーパーが8秒を超えてボールを保持した場合、相手側チームにコーナーキックが与えられる(第12条 ファウルと不正行為)
ゴールキーパーが手や腕でボールをコントロールすることに対する8秒制限の、残り5秒をカウントダウンする。
これまでは、ゴールキーパーが自分のペナルティーエリア(以下、PAと略)内で、主審がボールを放すまでに手や腕で6秒を超えてコントロールしていたと判断した場合、反則として相手に間接フリーキック(以下、FKと略)が与えられていました。
今回の改正では、主審が8秒を超えていると判断した場合、ゴールキーパーがいた側に近いコーナーエリアから相手のコーナーキック(以下、CKと略)で再開します。2秒長くなりました。
さらに、ゴールキーパーが8秒を超えないでボールを放すことを目的としているので、主審は、ゴールキーパーが手や腕でボールを保持してから3秒が経過していても保持を続けていれば、目で見て分かるように、広げた手を挙げて最後の5秒を「5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 」と指を折り、声に出し腕も動かしてカウントし、その後、
また、カウントダウンを開始するタイミングは、ゴールキーパーが確実に手や腕でボールをコントロールした時からとなります。例えば、相手のクロスボールやシュートをキャッチした後、フィールドに横たわっていてもボールを明らかに保持していると主審が判断すれば、カウントを始めます。しかし、キャッチした後、味方や相手の選手によって囲まれてすぐにキックしたり、スローしたりできない場合はその選手たちが離れるまでカウントダウンの開始を遅らせます。その判断は主審に任されています。
一方で、これまで通り、相手選手はゴールキーパーがボールを手から放すことを妨げた場合、反則となります。審判員は、むやみに反則を見つけようとせず、周囲に影響されずに、より円滑な試合を運営することが求められているように思います。
ゴールキーパーの手による使用制限の歴史は長く、ゴールキーパーによる、いわゆる「時間稼ぎ」を防ぐ努力を1964年東京オリンピック頃から続けています。1966年の歩数の制限であった「4ステップルール」から、2000年の時間の制限である「6秒」を経て、現在の競技規則になっています。できるだけゴールキーパーによる時間の浪費をなくし、フィールドにボールを戻してプレー時間を長くしようという狙いがあります。
自分のチームが利益を得るかどうかではなく、さらに観客を退屈にさせないためではなく、サッカーを面白味のないスポーツにしてしまわないという基本的な理念に基づいて改正されたように考えます。
これまで、この反則がPA内の間接FKとなると得点に結びつきやすく、主審としては非常に難しい判断に迫られなかなか罰則を適用することができなかったのではないかと思われます。今回の改正で、再開がCKとなり、どのように変わるのか楽しみです。
ドロップボールによる再開方法が変更になる(第8条 プレーの開始および再開、第17条 コーナーキック)
今回の改正により、ボールをドロップする場所、そして状況によって、どちらのチームにボールをドロップするかが変更になりました。
プレーが停止されたとき、ボールが
• PA内にあった場合 ⇒ ボールは、PA内で守備側チームのゴールキーパーにドロップされる(これまで通り)
• PA外にあった場合 ⇒ 基本的にはボールを保持していたチーム、あるいは最後にボールに触れたチームにドロップされます(これまで通り)
しかし、
• 最後にボールに触れたチームの相手選手に渡ろうとすることが明らかな場合、ボールは渡ろうとするチームの選手にドロップされます(改正)
• 主審が明らかでないと判断すれば、最後にボールに触れたチームの選手に、プレーが停止された時にボールがあった位置でボールはドロップされます(改正)
• プレーが停止された時に、ボールがPA外にあった場合の再開場所が、今までは最後にボールに触れた選手の位置でしたが、プレーが停止された時にボールがあった位置に変更になりました(改正)
例えば、PA外で、AチームがキックしたボールがBチームの頭に直撃し、そのボールがAチームの選手に明らかに渡ろうとしているところでプレーを停止したならば、その時にボールがあった位置で、Aチームの選手にボールをドロップします。ただし、主審が頭にボールが当たったので即座に笛を吹いて停止した時、どちらのチームにボールが渡るかどうか明らかでないと主審が判断したならば、停止した時にボールのあった位置で、最後に触れたBチームの選手にボールをドロップして再開します。
キャプテンオンリー:主審は基本的にキャプテンに対して重要な判定を説明することができるようになる(第3条 競技者)
各チームには、フィールド上に(キャプテンとして)識別できるアームバンドを着用したキャプテンがいなければなりません。チームのキャプテンは、なんら特別な地位や特権を与えられていませんが、そのチームの行動についてある程度の責任を持っています。
いろいろな大会では、フィールドにいる選手の振る舞いを改善し、選手と審判員の協力関係を高め、信頼関係をより良くするために「キャプテンオンリー」のガイドラインを使用することが勧められています。これまで同様、主審が決定したことに対して、透明性を高め、不満や対立の可能性を回避するために選手と主審との通常のやり取りは認められています。そして、キャプテンを含め、言葉や行動で異議を示す選手は警告されます。
今回のガイドラインにより、キャプテンまたは事象に関わった選手に重要な決定について説明できるようになります。誰と話しをするかは主審の裁量に任されています。キャプテン以外では、例えば、反則を行った選手、あるいはファウルを受けた選手、あるいは負傷した選手が対象となります。各チームから主審に話しかけることができるのは一人の選手のみであり、通常はキャプテンがその対象となります。主審は他の選手に主審自身とキャプテンに近づくことがないように、口頭または身振りで指示または促すことができます。キャプテンも同様にチームメイトを主審から遠ざけるように働きかける責任があります。許可されていないにも関わらず、主審に近づいたり、取り囲んだりする選手は警告されることがあります。
必要に応じて、主審は、キャプテンがチームメイトに決定を説明したり、適切な行動を求めるなどの話しをしたりする時間を与えるために、プレーの再開を遅らせることがあります。ゴールキーパーがキャプテンである場合、ゴールキーパーの代わりに誰が主審に話しかけることになるのかを、キックオフの前のコイントスまでに主審に伝えることになっています。あるいは、主審から選手に尋ねることになるでしょう。
このガイドラインが実施されることで、選手と審判員との協力関係、そして信頼関係がさらに高まり、主審が重大な判定を下した後、取り囲まれたり、威嚇されたりすることがなくなり、サッカーという競技のイメージが守られることが期待されています。
チーム役員などが競技のフィールドから出ようとするボールに触れたが、不正に妨害しようとする意図がなかったときの再開と懲戒の罰則の考え方が追加される(第9条 ボールのインプレーおよびアウトオブプレー)
これは、監督等が、ボールが外に出たと勘違いして触れてしまった場合などの対応です。チームスタッフや控え選手などがピッチから出そうなボールに触れ、それが不当に影響を与えようとする意図がない場合、カードの対象とはせずに間接FKで再開します。

今回の改正によって、選手・チーム、レフェリーチームが今まで以上に協力して、美しいサッカー、面白いサッカーが展開されることを願っています。レフェリーチームは、改正された競技規則とその精神を深く理解し、正しく解釈し、現場で選手のために適用していきたいものです。