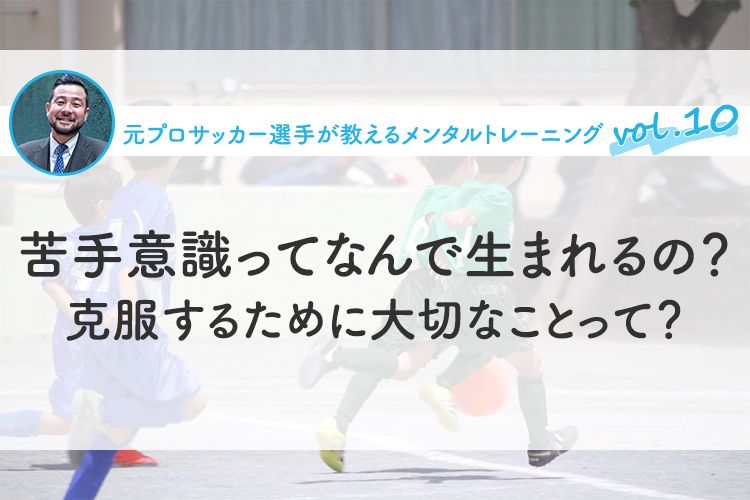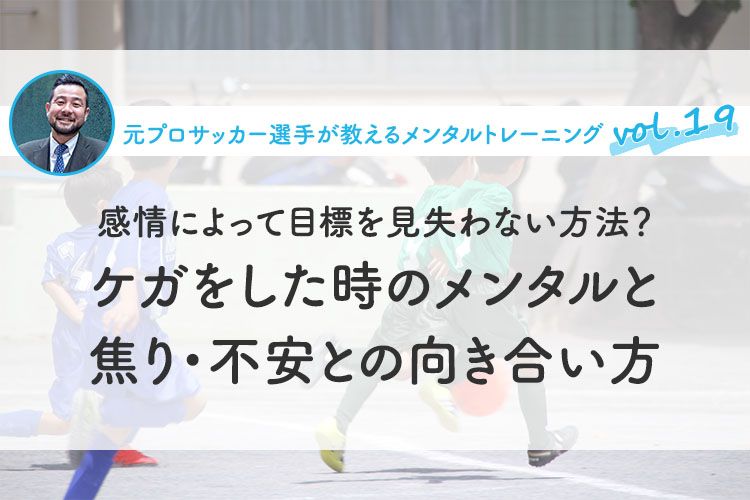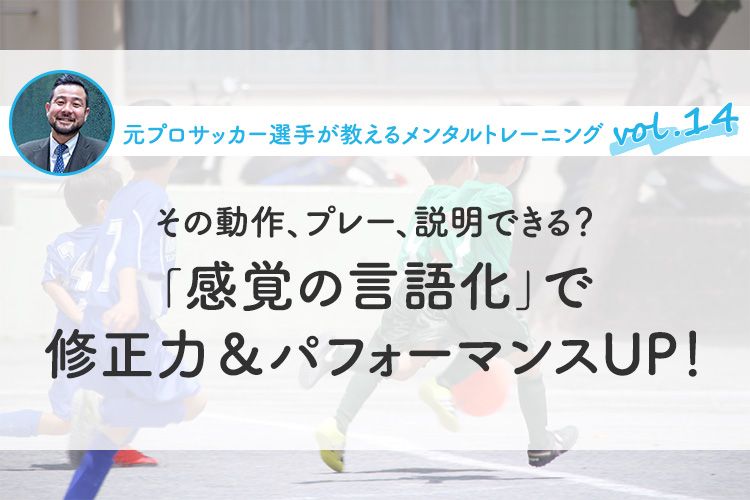苦手意識ってなんで生まれるの?克服するために大切なことって?
元プロサッカー選手で現在はメンタルトレーナーとして活動する山下訓広さんによる連載第10回目。
今回のテーマは「苦手意識」。どうして苦手意識が生まれてしまうのか、そして、苦手意識を克服するために大切なポイントとは?
得意・苦手意識ができるのはなぜ?
子ども達と接していると、自分の得意なことは進んで挑戦できるけど、苦手なことはやりたくない、という子が多いです。なんで苦手なことはやりたくないのか?というと、「失敗したくないし、失敗したら恥ずかしいから」とのこと。
確かに大人でも苦手なことはあまりやりたくないですよね。でも、やらないといけない時もありますし、苦手を克服しないといけない時もあります。そもそもなんで頭の中で「得意」「苦手」という感覚ができるのでしょうか?
マイナスの感情から苦手意識が生まれる
結論から言うと、得意や苦手といった感覚は「行動に対してどのような感情がわいてくるか」によって決まります。
私がサポートしている子の中に、新しいチームに入ったものの人と話すことが苦手でなかなかチームに馴染めない、という子がいました。サッカーは好きだけど、練習に行くことが億劫に感じてしまうことさえあるとのこと。そこで、その子に「人と話す時にどんな感情になるの?」と聞いてみたところ、「恥ずかしい」「怖い」といった感情をあげてくれました。
この子は「人と話す」という行動に対して、「恥ずかしい」「怖い」というマイナスの感情を抱いています。恐らくマイナスの感情を抱くことになった何かしらの経験があったのだと思いますが、このマイナスの感情を何度も味わってしまうと、「苦手」という感覚が出来上がってしまうのです。逆に、「人と話す」という行動に対して「楽しい」「嬉しい」といったプラスの感情を味わっていると、「得意」「好き」という感覚が生まれてきます。

苦手意識の克服には、頑張ればクリアできる目標設定が大事
さて、人と話すのが苦手だというこの子。そこで私は、「まずはお友達みんなの名前を覚えることから始めよう」と提案し、「○○君おはよう!」と自分から挨拶はできるか聞いてみました。すると、会話は難しいけど挨拶ならできると言ってくれたので、チームメイトの名前を少しずつ覚え、自分から挨拶することに挑戦してもらいました。
その後、改めて話を聞いてみると、みんなに挨拶ができるようになり、会話も少しずつ増えてきたと教えてくれました。練習に行くことも楽しみになったとのこと。そして、「名前を呼んで挨拶したら、挨拶が返ってきて嬉しかった」と話してくれました。「自分から挨拶する」という行動に対して、挨拶が返ってきて嬉しい、挨拶ができたという達成感、といったプラスの感情を味わえたようです。ここから少しずつ、「人と話す」ということに対する苦手意識も解消できたのでしょう。
このように、どんな感情を味わうかによって自分の中にできる感覚が決まってきます。何か苦手なことを克服したい時は、いきなりその苦手意識があることに挑戦するよりも、頑張ればクリアできる目標設定をしてあげると「達成感」や「喜び」といったプラスの感情を味わうことができます。それを積み重ねていけば、もともと苦手にしていたことも克服できるはずです。

苦手意識を克服するために、保護者ができることは?
これはもちろんサッカーでも同じことです。ドリブルやパス、シュート、1対1のディフェンスなど、それぞれ苦手なプレーがありますよね。それを克服したいのであれば、まずは頑張ればできそうな目標設定を考えてみましょう。例えば、シュートが苦手であれば、「今日はシュート練習で3回は枠の中に入るように打とう」であったり、パスが苦手であれば「狙ったところに5回はパスを通すようにしよう」など具体的な目標設定をしてあげると、よりプラスの感情を味わいやすくなると思います。
あまりにも高すぎる目標は、達成できずに逆に苦手意識が大きくなってしまうこともありますから、保護者の方はその辺りを注意しながら、本人の苦手意識や技術レベルに合わせて、お子さんが丁度いい目標を設定できているか見てあげるといいと思います。
また、感情を評価することはNGです。「なぜそんなことが恥ずかしいの?」「なんでそんなことが怖いの?」など、子ども自身が抱いている感情を大人の物差しで評価してしまうと、余計に苦手意識が大きくなってしまいます。感情は自然に湧き出てくるものです。恥ずかしくなりたくて恥ずかしくなっている子どもはいませんし、大人もまた同じだと思います。
大切なのは、子どもがなぜ苦手意識を抱いているのかを一緒に探っていくことです。そして、その原因に対してプラスの感情を味わえるように、適切な目標を一緒に考えれば、少しずつ苦手意識も克服できるでしょう。苦手意識を克服して、よりたくさんのことに挑戦していけるように、お子さんのお手伝いをしてあげてみてくださいね。