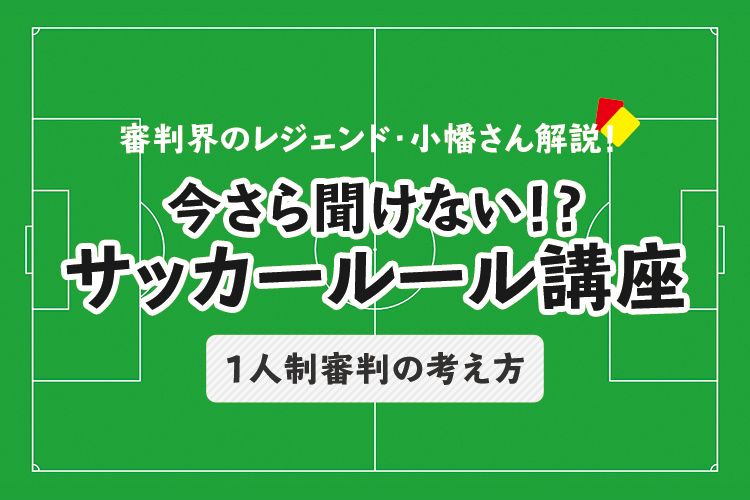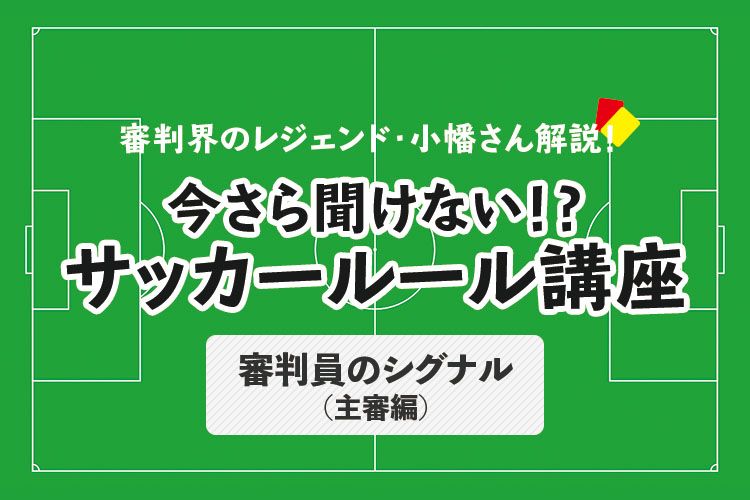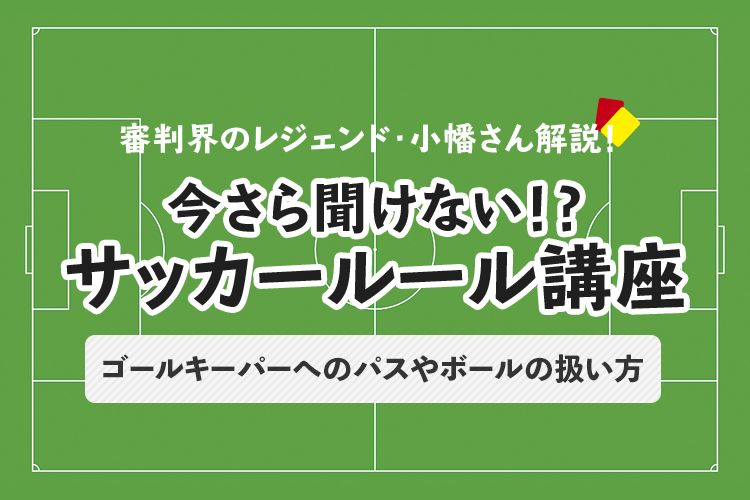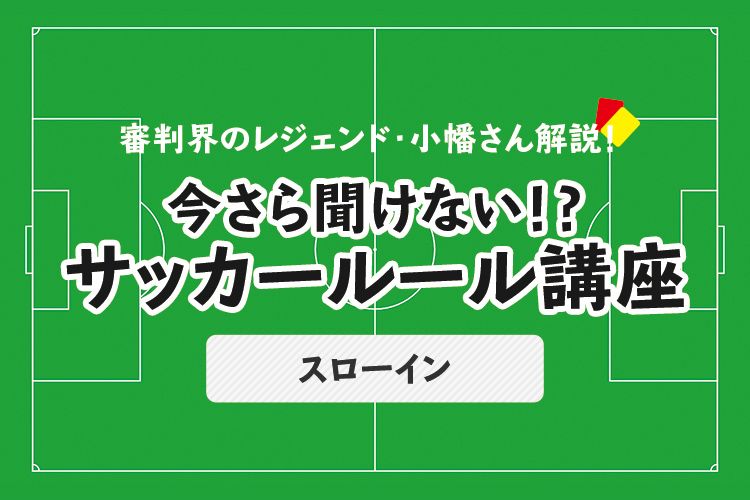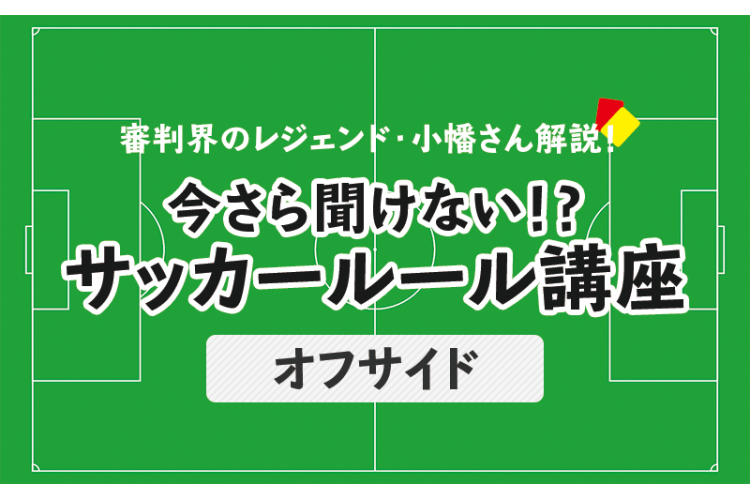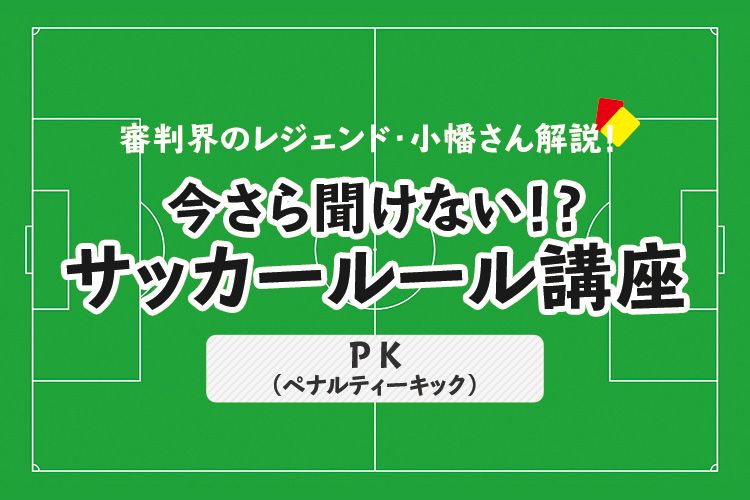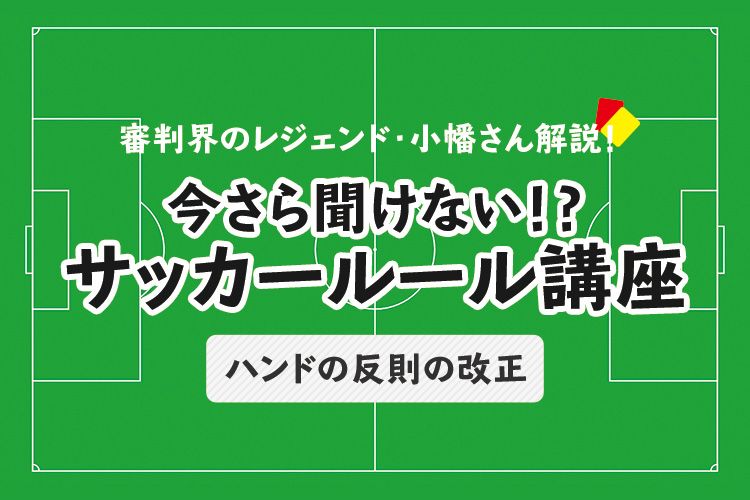今さら聞けない!?サッカールール「1人制審判の考え方」
1993年のJリーグ開幕戦で主審を務め、審判界に多大な功績を残したレジェンド・小幡真一郎さんによるサッカールール解説シリーズ!
今回は「1人制審判の考え方」。8人制サッカーの審判は主審1人。フィールドが狭いとはいえ、1人で全てを見るのは大変です。どんなことを心掛けておくといいのでしょうか?
8人制サッカーの目的と審判の役割

まずは、8人制サッカーの目的を振り返っておきたいと思います。以前にも取り上げましたが、サッカーはルールの中で自由な発想を大切にしますので、選手一人ひとりがどこに動くのか、どんなプレーをしたらよいかなど、多くの判断が求められます。
8人制サッカーでは子供たちがボールにたくさん関わることで判断の回数が増え、11人制よりも観るものが減ることによって何を判断すればよいのかが明らかになります。また、攻守にわたり積極的に関わることでサッカーの全体像を理解し、関わることの習慣づけができます。何よりも、プレーの回数が増え、成功と失敗を繰り返すことにより、自分と味方、味方と相手、自分と審判など、サッカーの理解が深まることにつながると考えます。
子どもたちがサッカーの理解を深めていく中で、審判の大切な役割はその成長を手助けすることです。選手同士が決められないものを審判が決めていたという歴史的経緯からも、1人制審判では選手を信じ、選手の自己申告を基本にしたいものです。
子どもたちのゲームでは、ボールがタッチラインを明らかに越えたときはドリブルをやめて、相手にボールを手渡す光景が見られます。相手を蹴って倒してしまったら、プレーをやめて手を差し伸べています。すぐに審判が笛を吹く、あるいはシグナルを示すのではなく、選手たちの判断を待って、迷った時に分からなければ審判が決めるという姿勢を持ちたいです。みんなが迷いそうなところは見落とさないように、経験を活かして優先順位をつけて判断していくことが大切ではないでしょうか。
実際に1人審判をやるときの考え方

「1人制審判では選手を信じ、選手の判断を待つ」ということを意識しつつ、実際に1人制審判をやるときの考え方を取り上げていきます。
明らかなものだけを判定する
1人制審判では援助をしてくれる副審がいないので、見えていないことに対して判断を下すことはしないようにしたいものです。ボールがゴールラインを完全に越えているかどうか分からないものをゴールにしたり、攻撃側の選手の足がオフサイドラインを越えているかどうか分からないものをオフサイドとしたりしないことが重要です。明らかなものだけを判定するという姿勢を貫いてください。
一方で、「見えなくていい、判定できなくていい」とするのではなく、最大限の努力をし、「見ようとする、判断材料を集めて決断する」ことも大切です。例えば、オフサイドの判定をするには、オフサイドラインに入って判定する必要はありません。キッカーとボールの受け手を同時に見えるポジションを見つけて、ボールがけられた瞬間に攻撃側の選手がオフサイドポジションにいたかどうか、全体を見て判断しましょう。また、試合前にハーフウェーラインやペナルティーエリアラインを使って、攻撃側選手と守備側選手の位置関係を把握するようなリハーサルをしておくのもよいのではないでしょうか。
広い視野で試合の展開やボールの流れなど全体を見て、次の展開を予測する
フィールドを走り回って、近くで判定することは難しいです。次に起こりそうなことを予測して見える位置に柔軟に動く、視野を確保することが大切です。ボールを持っている選手がどこを見ているのか、誰がボールをもらいたがってどこに動いているのか、どこにスペースがあるのか、守備側がどこにいて、どの方向に動いているのか、ゴールキーパーはどんな指示をしているのかなどの情報を得るようにします。それには、顎をあげて遠くを見たり、ボールがアウトオブプレーのときに周囲を見渡したり、ボールが来る前に自分の背後を見たり、耳を澄ませて選手の声を聴いたり、いろいろな情報を取り入れることです。その結果、自分がイメージした次のプレーが実際に起こると嬉しいものですよ。
ファウルを探すのではなく、安全にプレーを続けられるかを見る
ゲームを楽しむためには安全な環境をつくらなければなりませんので、攻撃的で危険なプレーはファウルとして判定する必要があります。とはいえ、積極的にファウルを探しにいくというのは違います。見てほしいのは、選手が安全にプレーを続けることができるかどうかです。決して、ファウルを探したり、見つけようとしないことです。
審判にとって大切なのは準備と振り返り
いろいろな判定を下すには、その起こったことをまず見ないと判断できませんので、見る準備をすることです。そのためには、全体を見ることができ、さらに部分を見ることができるポジションに動くことが大切となります。瞬間移動はできませんので、選手の様子やボールの動きなど、得た情報をもとに、いつでも動ける心づもりをして、サイド・バックステップなどを使って見えるところを探すことです。この探す作業が審判の面白さと言えます。近くで笛を吹くことより、きちんと見えるところで笛を吹くことを大切にしてもらいたいです。
また、笛を吹くと決めたら、迷わずに吹いてみてください。そして、選手の反応を感じてください。「OK」という声を聞くときもありますし、「えー」という顔をされるときもあります。それは、ゲーム後に振り返ればよいので、気持ちを切り替えて、次のプレーを見るところを探していきましょう。その繰り返しがうまくなる秘訣だと思いますし、私自身、選手からたくさん教えてもらって成長したと声を大にして言えます。審判は試行錯誤の連続ですので、是非いろいろチャレンジしてみてください。
選手にとってゲームは最高のトレーニングの場です。練習では経験できないさまざまなことに仲間と立ち向かい、解決することによって、楽しむだけではなく選手として成長していくと思います。そして、審判も試合で成長していくものだと感じます。
今年はなかなか集まることが難しいですが、電話やメールなどで成功と失敗を仲間と共有してください。そうすると、審判も子どもたちと一緒にさらに成長することができるのではないでしょうか。