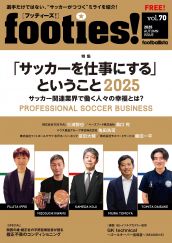知らないと損する!?「ルール改正」で覚えておくべき6つの基準 #2
IFAB(国際サッカー評議会)から2019-20年のサッカー競技規則改正が通達され、国内ではJ1リーグで8月2日から、地域別に段階的に新ルールが適用されている。「プレーイングタイムの確保、選手間のマナー、リスぺクトの向上」などを目的とした今回のルール改正により、選手たちが覚えておくべきポイントは!?
1993年のJリーグ開幕節で主審を務め、審判界に多大な功績を残したレジェンド・小幡真一郎氏に、特筆すべき変更ポイントをピックアップし、解説をいただいた。覚えておくべき6つの基準を3回に分けて紹介する。
★前回紹介した変更点は…「ゴールキックに関する改正」「フリーキックの壁入り禁止」
変更3:交代時は近くの境界線から

交代が告げられた選手はハーフウェーライン付近からピッチを去るのが一般的でしたが、新ルールでは主審からの指示がない限り「境界線の最も近い地点から出なければならない」となりました。
ここがポイント!
あからさまな遅延行為を阻止し、試合展開をスピーディにすることが目的です。ただし、必ずしも『最も近い』境界線でなくても、走って速やかにピッチを出られる距離であるならば警告にはなりません。そこはレフェリーの裁量となります。当然ながら明らかに離れた距離からハーフウェーライン付近に向かうようであれば警告の対象となります。私個人の見解としては何でも杓子定規にやればいいというものではないと思います。勇退する選手へのスタンディングオベーションなど、サッカーにはエモーショナルな交代シーンというものがあります。そこは臨機応変に対応すべきだと思います。
変更4:ドロップボールの変更

ドロップボールで再開するとき、従来は両チームの選手が何人でも参加することができましたが、ルール改正により「最後にボールに触れたチームの競技者の1人」だけが参加することになりました。この時、他のすべての選手は4m以上ボールから離れなければなりません。
ここがポイント!
ドロップボールによる無用な対立やトラブルを起こさないためのルール改正です。これまではドロップボールはどちらの過失もない状況で行われるもので、先にボールを触った方が相手チームに返すのがマナーとされてきました。フェアプレーの一環としてこのようなマナーがありましたが、あくまで暗黙の了解であり、『返さなければならない』とルールブックに記載されているわけではありません。今回のルール改正で明確化されたことにより、ドロップボールからチャンスへ直結する場面もでてくるでしょうし、試合はよりスピーディになるでしょう。
また、今まで主審に当たったボールで攻守が入れ替わり攻撃のチャンスとなったり、直接ゴールに入ったりすることはなくなり、ドロップボールでの再開となります。ですので、リスクを冒してでも近くで判定できるようになり、胸をなでおろすレフェリーもいるでしょうが(笑)、私からすると『(ボールに)当たるも未熟』という思いもあります。ルールに寄りかかるのではなく、審判員も常に技術を上げていかないといけないと考えます。