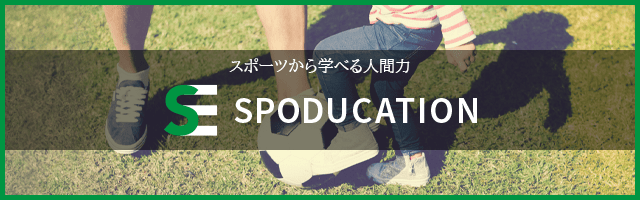Jリーガーたちの原点「石川 直宏(FC東京)」
小学生時代から大切にした反復練習。地道な練習が高い技術の源になった
日本代表監督アルベルト・ザッケローニをして「スピードと相手が予測し難い意外性を併せ持つ」と言わしめた石川直宏。子ども時代の話を聞いて彼に抱いた印象は“負けず嫌いの、ポジティブ”なサッカー小僧だった。彼がサッカーを始めたのは幼稚園のとき。近所で一緒に遊ぶお兄さんたちの影響でサッカーを始めた。とにかくサッカーが好きでたまらない。いつもボールと触れ合っていた。「サッカーは遊びの延長線上でした。公園でもやるし、自分の家の前のアスファルトでもやっていました。家の中でボールを蹴って怒られたこともありましたよ(笑)。土日はチームに入って広いグラウンドでサッカーができる。みんな同じユニフォームなので、仲間意識みたいなものも芽生えました。とにかくサッカーをすることが楽しかったですね」
小学生時代のポジションは攻撃的MFのトップ下。キャプテン的な素質も発揮した。「点が取れて、なおかつ自分がボールに多く触れられるポジション。それは、自分が目立ちたいとかではなく、トップ下なら自分がどうにかすればチームが勝てるような気がしたし、周りの選手を活かせるパスを出せばみんなも反応してくれて、信頼関係みたいなものを感じる楽しみもありました。ただ、当時は色々なレベルの選手がいたし、チームのレベルもさまざま。僕らのチームは強かったので、大差で勝つこともあったんです。そういうとき、普段は試合に出られない子に出場機会が回ってくるんですけれど、なかなかボールには触れないんですよね。でも、その子にも気持ちよくプレーさせてあげたいので、相手のことを考えてパスを出したりしていました。相手を思う気持ちみたいなものを、早い段階で自ら気づけたことは大きかったですね」
小学生時代に培ったのは、仲間を思いやる考え方だけではない。技術面でも当時の練習が大きな影響を及ぼしている。「小学校のときは基本の反復練習。最初はリフティングからスタートして、ドリブル練習をやっていました。単純な練習なので飽きてしまいがちなんですけれど、当時の指導者の方も色々と工夫してくれました。例えばドリブル練習では、技術がおぼつかないと頭が下がってしまうんです。それを何とかしようと、監督やコーチがドリブルをしていく先に立っていて、『ハイ!』と言って指で数を示すんです。それをドリブルしながら見る。その手を見ることで、ちゃんと頭を上げるクセを付けさせるんです。あと個人的には、一対一とかも周りの選手に負けたくなかったので、みんなと競争しながら一生懸命やりました」
地道な練習で技術を身に付けた石川少年。プロサッカー選手になりたいとの夢を抱いていた彼は、地元の横浜マリノスジュニアユース追浜へ進む。ときを同じくしてJリーグが誕生。しかし、そこで大きな挫折を味わう。「小学校のときは、何があっても挫折とは思わず、楽しんでサッカーをやれていました。すごい選手がいると知ったときは、悔しいとか、アイツに勝ちたいとかいう気持ちもありましたけれど、それも『上に行くには、彼らよりも上手くならなければ』という感覚ですよね。ユースに入ることにも迷いはありませんでした。よりレベルの高いチームにいけばいくほど上手い選手は集まるけど、切磋琢磨して自分も上手くなれば、また夢や目標に一歩近づく。そういうビジョンが小さいときからハッキリしていましたから。ただ、中高生のときは本当に苦しみました。上手くプレーできた機会は、数少ないと思います。反復練習のおかげで、他の選手よりも基本的な技術の精度や質は高かったと思うんですけど、中学になると、そこにスピードやパワーが必要になってきます。自分は成長が遅かったので、それがない。周りの選手は、身体能力で技術をカバーできてしまうんです。自分が生き残るために、より技術面を磨いていましたね」
そんな苦しみのなか、さらにトップ下から、サイドアタッカーへの転向を命じられる。「トップ下にこだわりがあったので、すんなりとは受け入れられなかったですよね。でも、そこで違う視点から見てみようと思ったんです。トップ下の視野は360°だけど、サイドの選手の視野は180°。サイドでプレーすれば、受けやすいボールとか、ゴールに対してのプレーだとか、細かい部分を考えられるようになる。サイドアタッカーになろうというのではなく、むしろトップ下として自分のプレーの幅を広げるんだというくらいの気持ちでした。納得できず、たぶん相当ふて腐れた顔をしていたと思いますよ(笑)。でも、そこでしか試合に出られる道がなかったし、トップ下の選手の気持ちも理解できれば、もっと良い選手になれると言い聞かせました」

苦しんだことも前向きな発想で克服。温かく見守る両親の存在も大きかった
持ち前の前向きな姿勢で、徐々にサイドアタッカーとして成長。後にFC東京の監督を務めた原博実は、「とにかく走る姿がキレイだった」と石川について語っている。しかし、本人から出た言葉は意外なものだった。「小さい頃からの負けず嫌いで、短距離も長距離も走るのは速い方でした。でも中学に入ってからは、スピードが通用しなかったんです。だから、走ることでは負けを認めて、体のキレで勝負することを考えました。足を速くするようなトレーニングもしなかったです。それよりも今、自分にできる技術を伸ばすことを考えていました。現在の走り方は特徴的だと思いますが、走りの質が変わったのはトップ下から、長い距離を走るサイドへ転向したとき。ストライドを大きくすると自分でもスピードが出ている感覚になるし、走りの気持ちよさを感じる。それが自分の調子のバロメーターでもありますよね」
サッカーを続けられたのは、両親の存在も大きかった。口うるさい方ではなかったが、食事の面では厳しいことも言われたという。「両親は、僕が目指すものに対してサポートしてくれるというか、温かく見守ってくれるタイプでした。小学校のときも練習や試合で、周りの子がコンビニやファストフードを買って食べている中、うちはお弁当を必ず作ってくれました。ただ、どんなに忙しくても、疲れていても、朝ごはんを食べなかったら学校に行かせないし、サッカーの練習にも行くなと。そういう基本的なところは厳しく言われることもありましたね」
自らの経験から、親子の接し方では、程良い距離感が必要だと言う。「自分も親になってみてわかるのですが、何でもやってあげたくなるんですよね。でも、ひとりの人間として子どもをリスペクトしてあげることは大事だと思います。僕の親は厳しいことを言わなかったけれど、逆に言われないことによって、子どもながらに自分で考えるんです。その考える時間を作ってあげれば、子どもでも自分なりの責任感が生まれる。逆にガミガミと言われていた子は反抗していましたよね。うちはそういうスタンスで接してくれて、自分で考える時間もあったので、それが良かったんだと思います」
将来プロを目指す子どもたちへは、「ボールと触れ合うことと、何でもいいから自分の中で得意とするストロングポイントを身に付けてほしい。プロは長所がひとつでもあれば生き残れる世界だから」とアドバイスを贈る。 ベテランの域に入った石川を現在も支え続けているのは、サッカーが好きで地道な練習に励み続けていた小学生時代にほかならない。
取材・文/宮坂正志(SCエディトリアル)写真/藤井隆弘
2012年12月発行の4号掲載