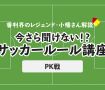【GK TECHNICAL】1対1の構えとシュートの対応
GK向けの練習メニューを紹介する「GK TECHNICAL」。
今回のレッスンテーマは、「1対1の構えとシュートの対応」。
今回は1対1の場面での正しい構え方とシュートストップについて。試合ではGKの真価が問われるシーンだけにしっかり身につけましょう。
LESSON1は、ボールの位置によるポジショニングと相手との間合いを詰めた際の構え方について、 LESSON2は、実際に相手との間合いを詰めた後の対応を紹介します。
LESSON1 ボールの位置に対するポジショニングと構え
写真1は、ペナルティエリアの外にボールがあります。相手の選択肢としては、主にシュートとドリブルなどがあります。シュートはGKの背後を狙う浮き球もあるため、GKはそれにも対応でき、なおかつドリブルで侵入されても間合いが詰められるポジションを取らなければいけません。よって、どちらにも対応できるよう、構えすぎず、軽く膝を曲げた姿勢を取ります。

写真2は1対1になった時の構え。間合いを詰めた際は背後へのシュートは選択肢としてなくなるので、構えを低くします。写真3と比較しても分かるように、身体の斜め前に腕を伸ばしたほうが、たとえシュートに反応できなかったとしても、腕に当たる可能性も高まります。


ボールがエリアの外にあるときはパスやシュートにも動ける姿勢をとりますが、1対1の場合は構え方もシュートコースを限定し、身体を広げる姿勢をとることで守れる可能性が広がります。
LESSON2 間合いを詰めた状態からのシュート対応
LESSON2は、実際のシュートへの対応です。最初は、キッカーが蹴る方向を決め、GKはそのシュートに反応します。しかし、試合ではキッカーは左右どちらにシュートするか分かりません。そのため留意点にもありますが、GKは必ずシュートを打たれてから反応すること。また、最終的には左右どちらにシュートを打たれても対応できるように、方向を決めずにシュートを打ってもらうなど、どちらにも対応できるようになると、セーブできる範囲も広がります。






間合いを詰めた想定で、まずは一方向にボールを蹴ってもらい対応する。最終的には試合状況と同じように方向を決めずに蹴ってもらい、ボールに反応できるようになろう。
留意点!シュートを蹴られる前に動かない
シュートする方向が決まっているからといって、打たれる前に動いて対応したのでは、試合でも「一か八か」の反応になってしまいます。必ず打たれてから対応する習慣を身につけましょう。



ワンポイントトレーニング
ボールを確実に弾く、セーブするトレーニング
ボールを触ることができても、確実に弾けず、失点してしまうケースは多い。確実に狙った方向へ弾くには、腕の位置、ボールを最後まで観る、腕の出し方を意識しながらトレーニングしよう。ここでは3つのトレーニングを紹介する。
テニスボールを用いたトレーニング
小さいボールをグローブをはめてキャッチするのは難しい。つかむタイミングを図ろう。

座った姿勢からボールを弾く

ボールをよく見て、斜め前方向にタイミングを合わせながらボールを確実に弾く。
基本姿勢からボールを弾く

実際には、この姿勢から反応するため、ボールの高さに姿勢を合わせながら対応する。
監修・文/松本拓也
写真/藤井隆弘